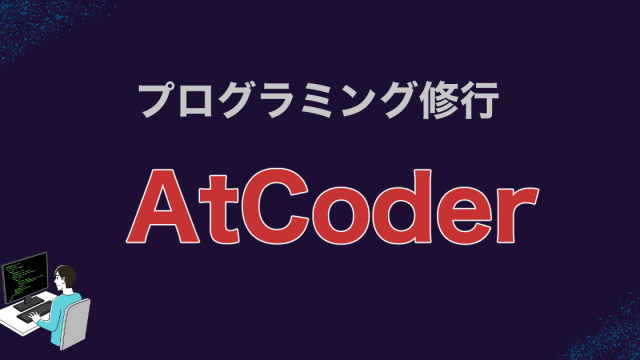少し前に、Udacityの「Data Engineering Nanodegree Program」に課金して勉強していたのですが、途中で放置していました。
とっくに期限が終わっていて、これが最後の振り返りになります。
期限切れてもアクセスできるらしい
久しぶりにログインしてみてはじめて気づいたのですが、コンテンツ自体には期限が切れても1年間はアクセスできるらしいです。
こんな感じで。

で、このリンクを進むと自分の学習状況が残っており、やり残しているコンテンツなどがわかっていて、コンテンツのページに飛ぶことができます。

Projectのページにも飛ぶことができますが、QAの過去ログは検索できなさそうです。でも、AWSには入ることができました。大丈夫なんでしょうか・・・ Udacityのセキュリティも心配ですが、それ以上に請求がこないか心配です。クレジットの登録は消しているので大丈夫だともいますが。
おそらく再課金すれば、サポートを受けられてプロジェクトを提出できて、最後まで完了させればナノディグリーというUdacityの修了証明をもらえるのでしょう。
私は当然課金しません。
サポートに価値は感じませんでしたし、ナノディグリーもいりません。他の人からしたら何それって感じですし、むしろ仮に持っていたとしても恥ずかしくて公言したくありません。Udacityの転職サポートも日本人には関係ないので、課金するメリットはまったくないですね。
まあ、それをいったら、そもそも最初からUdacityに課金するメリットなんてないでしょという話になりますが。
注意点、Udacityのいやらしい所
注意点として、Udacityの初期設定では、プログラムを終了しないまま期限を過ぎたら、自動で再課金するようになっています。いやらしいですね。
終了間際にログインして、念のため確認してみたら、そうなっていました。
気づいて良かったです。すぐにクレジットカードの登録を削除しました。
全体を通しての達成率
全体を通して、達成率を振り返ると、教育コンテンツは全部で4パートあって、内2パートは完了。残り2パートはプロジェクトの提出は通っていないものの、コンテンツ自体はほぼ消費したので、まあいいかなって感じがしています。
最後の「Automate Data Pipelines」の章は、Project提出すらいしていません。この章で学習する内容はAirflowだったんですが、このとき既にデータエンジニアの案件にジョインしていて、実務でAirflowを触っていたので、もういいかなという感じがして、やる気がまったく起きませんでした。
全体を通しての感想
修了には至りませんでしたが、まあ満足はしています。4,5万円ぐらいしたので、その価格ほど価値があったのかというと、困りますが・・・
当初の「データエンジニアについて効率よく学習して、データエンジニアの案件にジョインしてすぐに貢献できるようになる」という目的は果たせたので良しとしています。
Udacityは、学習内容とハンズオンの環境を提供してくれるので効率よく学習できるところが良かったと思います。
もちろん学習するだけなら、データエンジニアの書籍を数冊読んだ方が知識量は豊富になりますが、それだと時間がかかります。Udacityはそれらの要点を切り出して、動画にしているので、本格的な書籍を読む前の準備運動的な位置づけとして適しています。
まだハンズオン環境もあるので、サッと触ってみるというのも良いと思います。AirflowとかはAWSのマネージドサービスはないので、用意するのはそれなりに大変ですからね。(まあ、Docker imageはあるので、環境構築はさっとできますが)
まとめ
以上、Udacityを完了後(修了はしていない)の感想、振り返りでした。
修了していない私が言うのも何ですが、Udacityは要点を効率よく学習して、実務らしきものをちょっと経験してみたいという用途なら、やってみるのも良いと思います。
価格が高めなので、学習にお金かけるのは当然という価値観がある人に限りますが。また、Udacityを踏み台に仕事を得られることは期待しないほうが良いです。