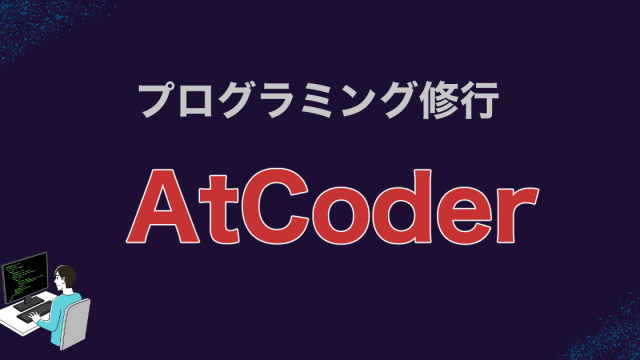こんにちは。タムタムです。
少し前に Udacity のData Engineering Nanodegree Programというコースを購入しました。
Udacity最初は75%引きというので、やってみる! pic.twitter.com/rkGzHFbzAZ
— tamtam (@tamtam15616309) January 13, 2022
今回はこのことについて書いていきたいと思います。
以下の様な人に参考になればと思います。
- リカレント教育に興味がある
- Udacityに興味があるけど、どんなものか知りたい
Udacityはじめる前に
はじめる前にあった疑問
私は半年ぐらい前からずっとリカレント教育に興味があったのですが、何をしていいのかわからない状態でした。ずっと以下の様な疑問を持っていました。
- リカレント教育って何やればいいの?
- Udacityって英語だけどついていけるの?
- Udacityのナノディグリーとって何か意味あるの? 良い会社に転職できるの?
- Udacityのナノディグリーより社会人大学院の方が良くない?
完全に答えた出たわけではありませんが、このことについても考察していきたいと思います。
現代社会はリカレント教育が必要って煽られる感がある
リカレント教育は、一言で言うと社会人の学び直しです。
背景として、技術の進化速度と人生100年時代で働く期間の増加があります。この2つの要因で、大学時代に学んだことだけでは定年まで通用しないので社会人でも学び直しが必要ですよ! というのがリカレント教育の思想です。
個人的には、大学時代の勉強はそもそも社会人になった直後から通用しないことが多く、働いている限り常に学び続けるのは必須と思っています。なので今更、改めて言うことなの?感はありますが。。。
国はこのリカレント教育のために大学院のプログラムの他、ちょっとした講座とかも用意しているのですが、いろいろ課題だらけです。
- 大学院のプログラムは高価
- 実プロジェクトに通用する講座は少ない
- リカレント教育しても、それを評価する社会になっていない(むしろマイナス評価をする企業がほとんど)
などです。
なので、これらの逆境を受け入れてでも学びたい人が、あくまで個人的な勉強をする程度がリカレント教育の現状です。
こういった穴だらけの社会インフラなので、Udacityのような教育コンテンツを提供している民間機関があるのだと思います。高価、やればマイナス評価を受ける、その上内容もずれている、となると厚生労働省が用意する教育プログラムを選択する理由はないですからね。
※ 社会人大学院を否定したいわけではありません。社会人大学院は人脈形成という大きなメリットもあります。自分が学びたい内容が提供されているなら、社会人大学院が一番の候補となると思います。
Udacityをはじめた理由
コースが豊富、自分が学びたい内容と一致する確率が高い
Udacityはコースが豊富です。選択肢がたくさんあるので、自分が学びたい内容と一致する確率が高いです。またUdacityのコース一覧を見ると、新たに自分が学びたいことが掘り起こされるかも知れません。
無料コースもあるのですが、正直使い物にならないかと思います。本気で勉強したいなら、お金を払うしかなさそうです。
初回割引率が大きいので1回やってみてもいいと思った
冒頭のTwitterの添付画像にあるとおり、初回は75%引きです。
それでも4万円以上するので安いわけではないのですが、巷にあふれている1ヶ月20万円ぐらいのプログラミング学習コンテンツに比べると安く感じます。こちらは5ヶ月間アクセスできますし。日本のプログラミング学習環境が異常なので比較対象として不適切ではありますが、これだけ割引があるなら1回はやってみてもいいかもと思いました。
Udacityのマーケティング戦略に踊らされた感はありますが・・・😅
(正規の価格ではとても契約する気にならないので、これが最初で最後のUdacityでの勉強になりそうです。)
なぜData Engineeringプログラム?
私は元々、スマートシティに興味がありました。近い将来これらに関する仕事をしたいと思っているのですが、今のスキルだと貢献できることは限られているので、何か学んでスキルを得たいと思っていました。
私の得意領域は一般的なITインフラとバックエンドです。これらを活かしつつ、スマートシティ関連の事業に必要になりそうな領域はビッグデータ関連、アナリティクスや機械学習エンジニアというよりは基盤よりかなと思って、その辺りを勉強したいと思っていました。
また少し前にデータ基盤構築の案件を請け負ったことがあるのですが、結局は裏でAWS Glueを動かして、その結果や元データにアクセスするAPIやUIを作っただけでした。ほとんどWebシステム構築の案件と大差なく、もっとデータ基盤についてがっつり経験したかったのにという消化不良の状態でもありました。
著書『シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成』を読んで、データがますます重要になっていく、データ整備できるエンジニアが不足しているということを知って、それに感化されたというのもあります。
データエンジニアについて学びたいと思ったのですが、厚生労働省のページをみる限り、マッチしそうな講座はありませんでした。なので民間企業をあたりました。私は英語が得意でないので、最初は日本語で学べるところを探したのですが、該当しそうなものはありませんでした。それどころか、Udactiy以外で見つけることができませんでした。なので英語というブロッカーはあったのですが、Udacityに飛び込んでみました。
Udacity ナノディグリーの評判
海外のレビューはいまいち
日本語では出てこないのですが、海外の人のレビュー動画がYouTubeに上がっています。
正直、Udacityの評価はいまいちな用です。
現役のフロンエンジニアがReactのナノディグリーの講座を受けたレビューは、まとめると以下の様な内容でした。
- 内容が古い。5年前ぐらいで実践的ではない。
- ナノディグリーという学位に価値はない。ナノディグリーはただの紙切れ。
いくつかレビュー動画を見たのですが、同意見の内容が多かったように感じます。
私はUdacity契約前にレビュー動画を見ていたのですが、それでも契約しました。
- とはいえ、Udacity以外にデータエンジニアの教育コンテンツがない。
- まあ安いし(75%引きなら)、効果がなくてもいい。何かしら得るものがあれば、それで十分。
といった理由からです。
ナノディグリーの意味
レビューでは、ただの紙切れと言われていましたが、本当にその通りだと思います。
Udacityは、講座を完遂すればGitHubにポートフォリオができてそれが企業から評価されてジョブを得ることができると謳っていますが、真に受けないほうがいいかと思います。
現役のエンジニアが転職したくなるような企業はそのようなポートフォリオを評価しませんし、仮に評価したとしても、私のような英語が話せないエンジニアは対象外でしょう。日本の転職市場でナノディグリー取りましたと言っても、企業はおろかエージェントも知らないでしょう。アピールすればするほど、マイナスになるだけのような気がします。
英語できないけどUdacity契約しちゃっていいの?
私の英語レベルは、TOEICでは600点未満です。それも英語を勉強していた頃、10年以上前の話で今はもっと酷いことでしょう。英語は苦手で、自分にも向いてないと思って、勉強は諦めました。
そんな私ではありますが、苦労はしているものの、何とかやっていけてはいます。
Udacityの教育コンテンツは、YouTubeと英語テキストです。YouTubeは日本語の自動翻訳と、英語表示で2回再生しています。正直、日本語の自動翻訳だけだと何が言いたいのかよくわらないことがありますが、その後に英語を表示しながら聞けば、だいたい理解できます。それでもちょっと分かりづらい箇所は、再生を止めて意味を調べたりもう1回再生したりしています。
本当に良い時代になりました。これが留学で実際に講義を聞くスタイルなら、まったくついて行けなかったでしょう。でも今は技術の力で、このような学習スタイルが可能になっています。英語ができないことは正直、それほどのデメリットではなくなってきたと思います。
テキストの方は、deepLに翻訳かければ、ほぼ完璧な日本語ドキュメントになります。これで理解できないなら、言語の問題ではなく、内容が難しいとか前提知識が足りないとかの問題でしょう。
最初は英語を読んで、その後deepLで内容を確認していたのですが、時間がかかってしょうがないので、今はいきなりdeepLに翻訳かけています。目的は語学の学習でないので、これでいいと思っています。
以上、Udacityをはじめた経緯とその感想になります。
近いうちに、勉強した内容なども記事にしたいと思います。